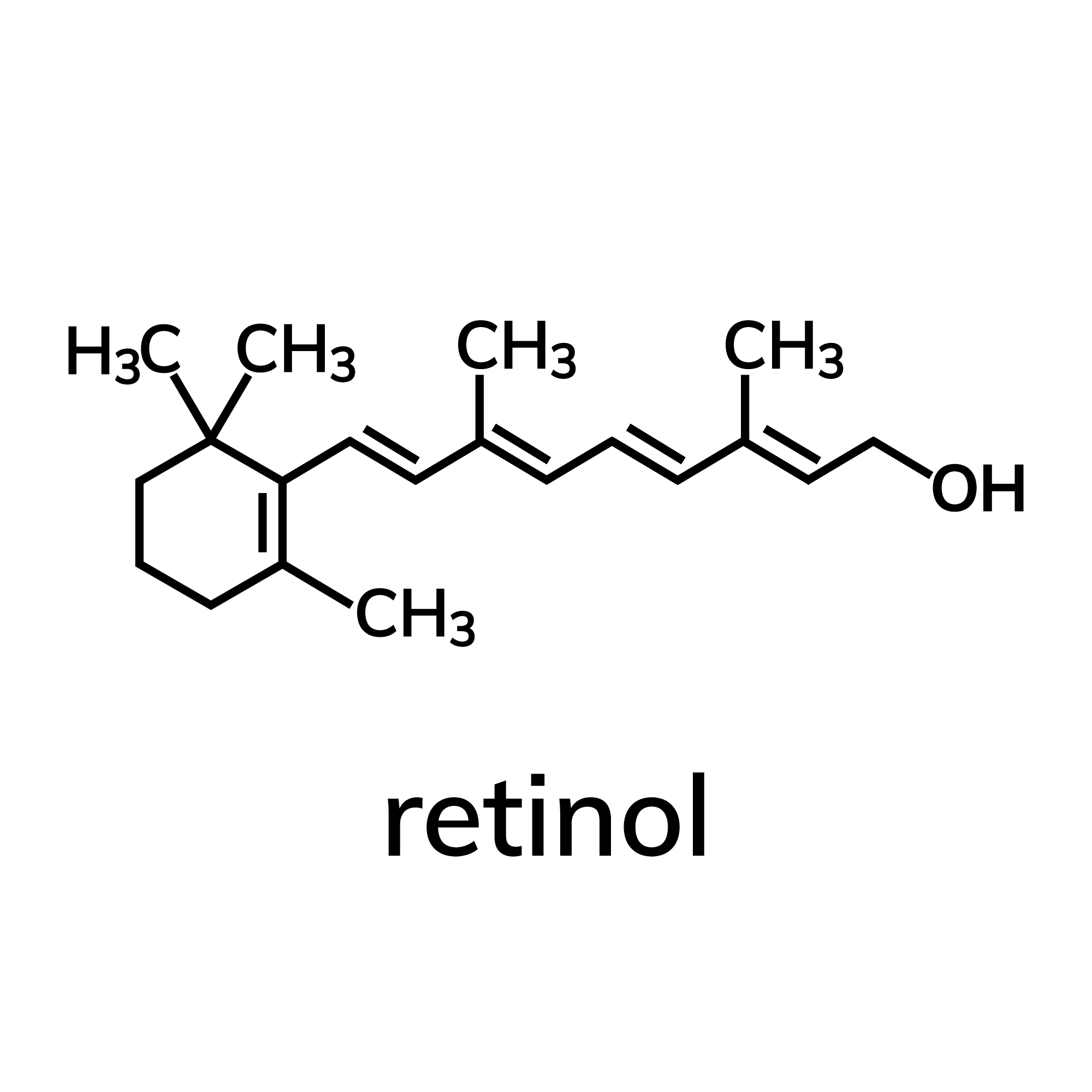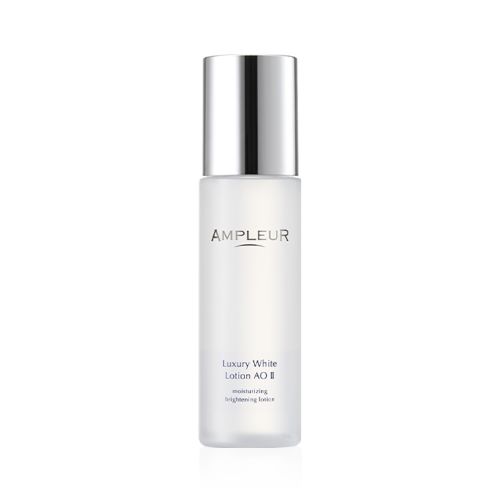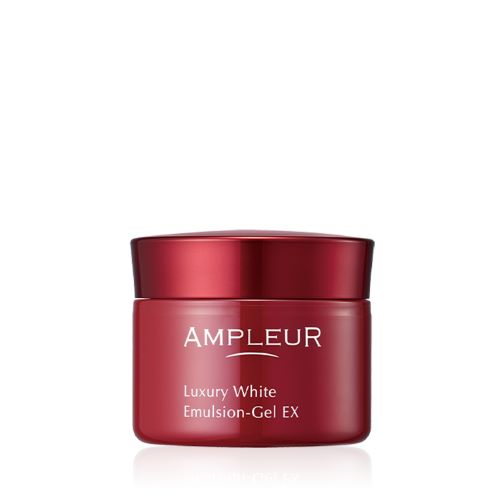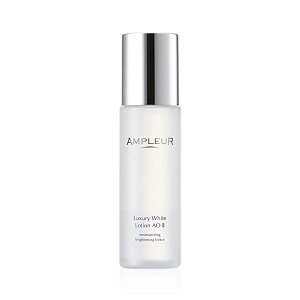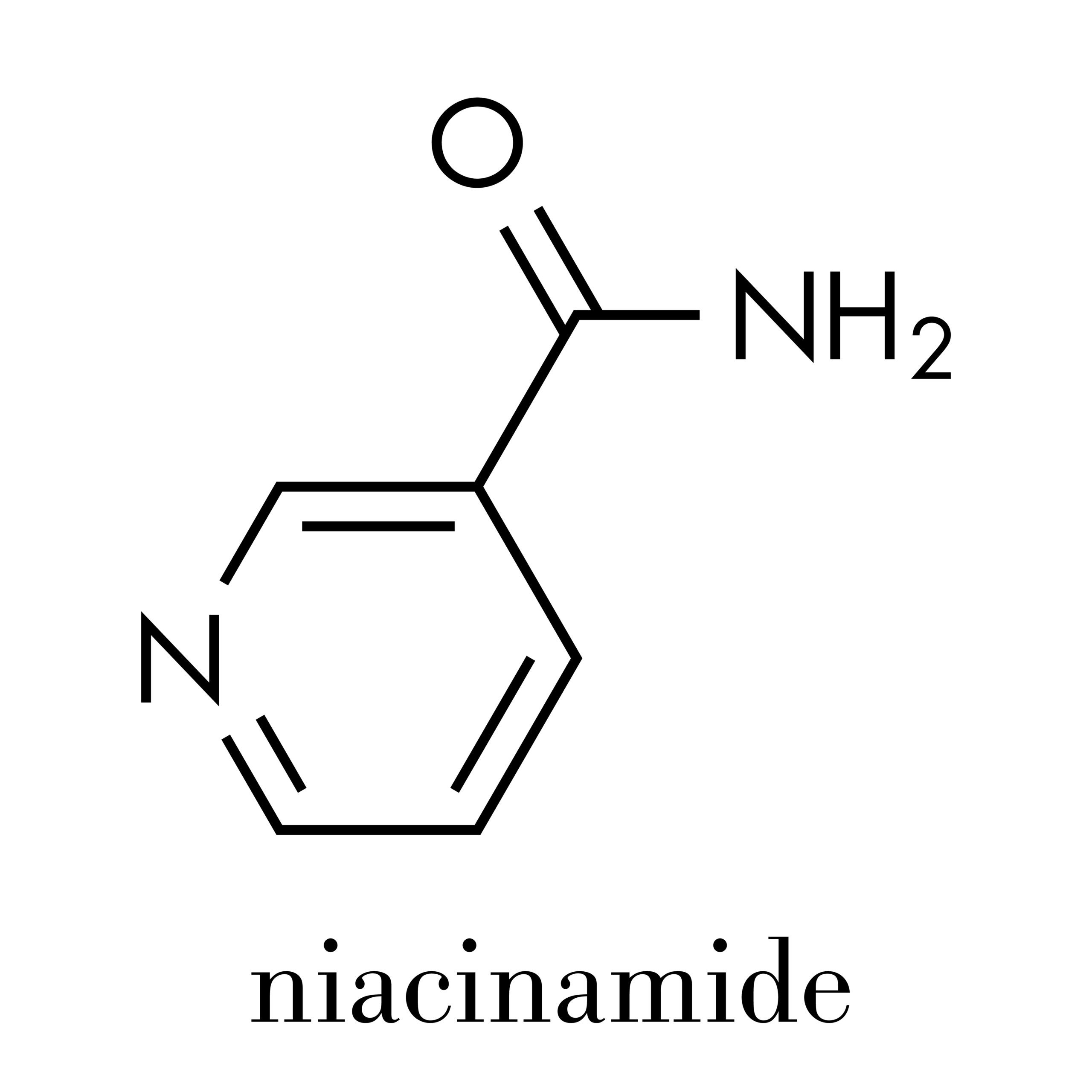スキンケアの最初のステップであるクレンジング。
メイクをきれいに落とせていないと、化粧水や乳液がなじみにくくなるだけでなく、ニキビや肌あれの要因になってしまう場合もあります。
トラブル知らずの美肌を目指すためにも、自分にあったクレンジングでメイクをすっきりとオフすることが大切。
そこで今回は、自分に合ったクレンジングの選び方や洗い方のコツをご紹介。よく耳にする「乳化」についても解説します!
そもそもクレンジングの役割とは?
クレンジングの基本的な役目は、ファンデーションやアイシャドウ・リップなどの「油性のメイク汚れ」を落とすこと。
それに対して洗顔は、汗・皮脂・古い角質・付着したホコリなど「肌の汚れ」を落とすのが役目です。
そのため、軽くでもメイクをした日はクレンジングが必須になります。
クレンジングの種類と選び方

クレンジングの種類は、クリームタイプ、ミルクタイプ、ゲルタイプ、オイルタイプ、ローションタイプ、バームタイプ、シートタイプとさまざま。
ほかにも、落ちにくいマスカラやリップをオフするためのポイントメイクリムーバーなどがあります。
それぞれのテクスチャーや洗い上がりの特長をつかんで、肌質や好みにあったものを選びましょう。
季節や肌のコンディションによってアイテムを変えてみるのもおすすめです。
1.クリームタイプ
敏感~普通肌&肌へのやさしさを求める人に
油分と水分をバランスよく配合し、適度な洗浄力を備えているのが特長です。
肌に必要なうるおいを守りながらメイクをオフできるので、乾燥肌・敏感肌・インナードライ肌の方に◎。
クッション性が高く、肌への摩擦を軽減してくれるところもポイント。
2.ミルクタイプ
乾燥~普通肌&ライトなメイクの人に
クリームタイプよりも油分が少なく洗い流しやすいミルクタイプは、洗浄力と保湿力のバランスが良好。
肌への刺激が抑えられるので、乾燥肌・敏感肌・インナードライ肌の方にも適しています。
3.ゲルタイプ
オイリー~普通肌&さっぱりな洗い心地を好む人に
ゲルタイプは、オイルフリーの水性タイプ、オイルインの水性タイプ、油性タイプの順に洗浄力がアップするため、購入前にチェックを。
密着力が高く、クッション性のあるテクスチャーで肌への摩擦を軽減しながらメイクを落とします。
さっぱりとした洗い上がりなので、脂性肌や普通肌の方と相性がよいでしょう。
4.オイルタイプ
普通肌&しっかりメイクの人に
配合しているオイル自体にメイクを落とす作用があるため洗浄力が高く、しっかりメイクもスムーズに落とせます。
クレンジング後の乾燥が気になる方は、メイクが濃い日だけ、といった使い方もOK!
また、酸化皮脂による毛穴詰まりをケアしたいときにも活用できます。
5.ローションタイプ
オイリー~普通肌&すすぎ不要で素早くすませたい人に
“水クレンジング”と言われることもあるローションタイプは、油分をほとんど含んでいませんが洗浄力はバッチリ!
コットンに含ませてメイクを拭き取るだけでOKなので、すすぎは不要です。
まつ毛エクステに使えるタイプもあります。
6.バームタイプ
乾燥~普通肌&しっとりとした洗い上がりを好む方に
油性成分を固めたバームタイプは、体温でとろけてオイル状のテクスチャーに変化。
しっかりメイクもするんとオフする洗浄力を備えています。
それでいて肌のうるおいを逃さずキープしてくれるので、つっぱり感のないしっとりとした洗い上がりに。
7.シートタイプ
オイリー~普通肌&場所を選ばずメイクオフしたい方に
クレンジング剤が含まれたシートタイプは、メイクになじませつつやさしく拭き取るだけでOK。
高い洗浄力で目もと・口もとの濃いメイクも素早くオフできます。
疲れてすぐに化粧を落としたいときや外出先などでも、サッと使える手軽さが魅力です。
8.ポイントメイクアップリムーバー
マスカラやリップなどの落ちにくいメイクをオフするときに便利なのが、ポイントメイクリムーバー。
洗浄力は高いですが、目もと・口もとなど部分的に使用するため、肌全体に負担がかかりにくいというメリットがあります。
※タイプの説明は一般的な見解です。実際の商品によっては異なる場合もあるので、ご購入の際には注意事項や使用方法等をよくご覧ください。
クレンジングの「乳化」って何?

クレンジングをする際は乳化が大切、と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。乳化とは、クレンジングに少量の水やぬるま湯を加えると白く濁る現象のこと。クレンジングに含まれるオイルと水が混ざりあうことで起こります。
乳化させるメリット
メイクや汚れが落ちやすくなる
乳化させることによって、からめとったメイク汚れや皮脂が浮きやすくなるので、よりすっきりとした洗い上がりに。クレンジングが本来持つ力を発揮させるための大切なステップだといえます。
すすぎ残しによる肌トラブルを防げる
乳化させると、クレンジングが落ちやすい状態になります。すぐに洗い流してしまうよりもすっきりするのはもちろん、すすぎ残しによる肌トラブルを防ぐこともできます。
油性だけでなく水溶性の汚れも落とす
肌の汚れには、メイクや皮脂といった油性のものと、ホコリや汗など水性のものの2種類があります。油性成分をが主要としたなクレンジングオイルなどは水性の汚れが落ちにくい傾向にありますが、水分を加えて乳化させることで、水性の汚れにもしっかりアプローチできるようになります。
肌への負担が減る
汚れが落ちやすくなる乳化を経ることで、クレンジングの時間を短縮できるだけでなく、肌への摩擦を減らすことにもつながります。また、クレンジングのテクスチャーがなめらかに変化することもポイント。やさしくすすぐだけでスムーズにメイクを落とすことができます。
乳化のやり方とポイント
乳化のステップはとても簡単です。
1.乾いた手で、顔全体にクレンジングをなじませる
2.クレンジングとメイク汚れがよくなじんだら、手のひらに少量の水、またはぬるま湯をとり乳化させ、顔全体へやさしく広げる
3.水、またはぬるま湯ですすぐ
ポイントは、顔全体が白濁するまでやさしくなじませること。ぜひ今日から気軽に取り入れてみてはいかがでしょうか。
ジェル・ミルク・クリームタイプのクレンジングの乳化は不要?
乳化は、オイルと水を一体化させることで起こる現象。そのため、クレンジングオイルの場合は乳化させることでよりきれいにメイクを落とすことができるようになります。
一方で、ジェルタイプは油分が少ないので、乳化させる必要がないものが多い傾向にあります。ミルク・クリームタイプはすでに乳化してあるような状態なので、こちらも基本的に乳化は不要です。
ただし、商品によっては乳化を推奨しているものもあるので、購入の際にチェックしてみてください。
クレンジングする際のポイント

1.ポイントメイクは専用クレンジングで最初にオフ!
ウォータープルーフのマスカラやアイライナー・落ちにくいリップなどは、ポイントメイク用やアイメイク用といった専用のクレンジングで最初にオフを。
メイクが残っていると肌トラブルにつながることもあるので、目の際をはじめ落としにくいパーツは綿棒やコットンなどを活用してやさしくきちんと落とすことを心掛けて。
2.肌に摩擦を与えないようやさしく洗う
使用量をよく確認してクレンジング剤を手に取ります。
量が少ないと肌に負担がかかりやすくなるので要注意。
また、メイクをしっかり落とそうとして、ゴシゴシと強く擦るのも絶対にNG!
Tゾーンからクレンジングをのせていき、顔の中心から外側へ肌を動かさないようになじませます。
3.小鼻などの細かい部分は指の腹で
小鼻など毛穴が詰まりやすいパーツは、指の腹を使ってくるくるとやさしくなじませましょう。
4.すすぐときはぬるま湯でしっかりと
水が冷たすぎると汚れやクレンジング剤が残りやすく、熱すぎると必要な油分まで一緒に落ちてしまいます。ぬるま湯でしっかりとすすぎましょう。
最後に
「なんだか最近、肌の調子が上がらない…」と感じたら、与えるケアだけでなく落とすケアにもぜひ注目してみてください。
肌に合わせたクレンジングを選ぶことで、コンディションが安定してくるはず。
こまめに肌と会話をしながら、美肌を育てる工夫をしていきましょう!